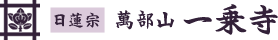副住職の1ヶ月日記

令和4年12月
我ら無知なるがゆえに
覚えず 知らず
少しき涅槃の分を得て
自ら足りぬとして
余を求めず
法華経五百弟子授記品
「幸せ(しあわせ)」の度合いは人によってさまざまです。仏教ではハッキリとした「幸せ」を示しません。それは、目の前のことに満足してしまうことが果たして、本当に「幸せ」と言えるのかどうかということです。
「幸せ」とは、真実の姿、本当の意味、真理を見極めることだと言えます。
君が無駄に過ごした今日は
昨日死んだ誰かが
死ぬほど生きたかった
明日なんだよ
(趙昌仁『カシコギ』より)
今も続くウクライナでの戦争、十月には韓国でハロウィーン中に起きた転倒事故等々で世界中では尊い命が失われています。一方、私たちは「今が良ければ」「また明日があるから」毎日をなんとなく過ごしてしまいがちです。この一日は私にとっての明日かもしれませんが、世界のどこかで昨日亡くなった誰かにとっては、かけがえのない明日だったかもしれません。
私だけのこと、過去のこと、これから先のことにとらわれずに今日この日一日を大切に生きていきましょう。
令和4年11月
日蓮宗総本山 身延山久遠寺第九十世法主
日勇上人のお言葉より
さぞ苦しいであろう。
さぞお困りだろう。
死んだ方がましだと考える、その気持ちもよくわかる。
だが、貴方よりもっと苦労しながら立ち上がった人がある。
もっと困っていながら切り抜けた人がいる。
絶望してはならない、人生には必ず活路がある。
人を呪うよりも自分の在り方を反省することだ。
人の幸福をうらやむよりも、自ら築くことに努めることだ。
そして神仏に仕えるつもりで人々に奉仕すれば、人々を幸いにするとともに、自分が幸いになる。
善人は人から重んぜられ、正義は人から尊ばれる筈である。
然し善人なればこそ悪人にきらわれ、正義なればこそ不正の輩に却けられる。
善人必ずしも重んぜられず、正義必ずしも尊ばれない。
だが悪人にして栄えたためしなく、不正にして誉れを得たものはない。
重んぜられずともよい。
私は善人でありたい。
尊ばれなくともよい。
私は正義であることを欲する。
令和4年10月
日蓮聖人のお言葉から
石中の火 木中の花
=秘めたる可能性=
この世の中には、自身の目では見えないものがたくさんあります。詩人金子みすゞは『星とたんぽぽ』という詩の中で、昼間の星やたんぽぽの根っ子は「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」と語りかけます。
私たちは目に見えない大事なものの存在を見落としがちです。私たちの内面には計り知れない可能性が秘められています。だけれども、なかなかそれに気づけないことのほうが多いのです。
昔は石を打って火を起こしましたが、普段石の中に火があることを見いだせますか? 枯木にどうして満開の花を想像できますか? けれども、きっかけや時が来れば今は見えないものが現れ出るのです。
だから私たちは信じましょう、今は気づいていない未来や大きな可能性があることを。
令和4年9月
日蓮聖人のお手紙より
迷う時は衆生と名付け悟る時をば 仏と名けたり
=仏を真似る=
お彼岸は、私たちの迷いをおさめ、善き心と行いを積み重ねることを勧める期間です。悟りと迷いの日々の中、人を救いたいというお釈迦さまのお気持ちにどれだけ近づき、同じような行いができるでしょうか…。
徳川光圀公は、巡行の折に、親を背負って行列を見せた孝行息子に褒美を取らせました。次の時、それを真似した悪童にも褒美を与えました。納得のいかない家臣に一言。「悪行を真似れば悪人となり、善行を真似するなら善人となろう。善きことを真似するのは、大いにけっこう」と、家臣を諭しました。
手を合わせるお釈迦さまのお姿は、すべての人やものを敬う尊いお姿です。私たちの生き方のお手本となります。人間の善き心と善き行いは、周りの人を幸せに導きます。まずは手と手を合わせる仏さまのお姿の真似をしてみることから始めてみましょう。
令和4年8月
人間らしく…
八月十三日から十六日までは、お盆月です。
ご先祖が、また戦争で、あるいは震災や頻発する多くの災害で亡くなった尊いいのち(命)に手を合わせ祈りを捧げる4日間です。
仏教と日本に古くからある先祖供養とが、うまく折り合ったのが「お盆」という年中行事です。
正式には「盂蘭盆(うらぼん)」といい、お椀に盛ったご飯をみんなに分けるという意味があります。
つまり、お盆には我が家の先祖だけでなく縁があった仏さん、縁のない仏さんにも平等に供養を行うことがお盆の本当の意味なのです。
今、諸外国では戦争によって尊い命が奪われています。日本ではこの時期台風、大洪水、そしてコロナウイルス感染によって突然に最愛の命との辛い別れがあります。
これら多くの今は亡き人々は、「人間らしい」最後、いわゆる「人間らしい」死を迎えられなかった方々です。
たとえ、肉親でなくても、面識のない人たちであっても、このお盆にどうか心からの祈りを捧げていただくことをお願いいたします。
「いのち」とは「意(い)・こころ(心)」の「地(ち)・落ちつく所」をいいます。
本来ですと、1年365日祈る心を大切にしたいのですが、忙しいこの世では難しいようです。
せめて、この4日間くらいは家族で、あるいは友だちと「いのち」について話してみませんか。
少しは、暮らしにくいこの世の中が変わって見えるかもしれません。
人間らしく生きることができたら幸せでしょうね。
令和4年7月
~日蓮聖人のお言葉~
異体同心なれば万事を成じ
同体異心なれば諸事叶う事なし
静岡では夏の高校野球が7月3日に開会し、9日からいよいよ試合が始まります。1人はみんなの為に、みんなは1人の為に、甲子園を目標に見据えて日々の努力をぶつけ合い熱闘する姿には毎年感動させられます。日蓮聖人は上記のようにおことばを残しております。
体は違っても心は一緒なら、どんなことも成就する。体が同じでも心がバラバラでは何も成功しない。
いつの時代も心を合わせることは最大の成果を生む秘訣です。私達は仏教徒として誰と心を合わせるのか?言うまでもなく仏さまです。仏さまの想いを知り、教えを学び、段々心を合わせていきます。
それが仏に成る。成仏するということなのです。
令和4年6月
~日蓮聖人のお手紙より~
人の地に倒れて 還て地に依りて 起つが如し
地にころぶも、起きあがるも同じところ。
つまり、人生での「つまづき」は誰にも
一度や二度は必ずあります。
しかし、倒れたままの人はいません。
母親が、友人が、同僚が必ず手を差しのべてくれるはず。
仏教では、自分にとって悪い行いがかえって仏道(信心)に入るきっかけとなることがあります。これを「逆縁(ぎゃくえん)」と言います。
たとえば、病気になることは嘆きでもありますが、今ままで気がつかなかった生きる悦びにも変わることを教えてくれるのが信仰なのです。
令和4年5月
~日蓮聖人のお手紙より~
著(き)ざれば風身にしみ、食(くらわ)ざれば命持(たもち)がたし
= 共に生き、共に歩む =
自分のお金で食材を買い、自分1人で調理して盛り付け。「いただきます」と掌を合わせたとき、「自分で作った食事なのに、誰に対していただきますしてるんだろう?」と思ったことはありませんか?私たちは1人では生きていけません。食事も衣服も、自分以外の他の多くの人・多くのモノと互いに支えあって生きているのです。この「いただきます」の習慣はそれらとの深い結びつき(縁)を受け止めるという「感謝」のことばです。支えあっているのですから、こちらからの発信、つまり他のために尽くすという行為がなくては成り立ちません。それが回り巡って自分自身に還ってくる。つまり他のために尽くすことが、そのまま自分を助けることとなるのです。
自分1人の利に駆られて他を害するなど、結果的には自身を傷つけることになるのです。
令和4年4月
~日蓮聖人のお手紙より~
けわしき山あしき道つえをつきぬればたおれず
= 一人で抱え込まないで =
針に糸を通すのは中々大変です。針を固定して糸の先を穴に通していたら、「糸を固定して針を動かすほうが通しやすいよ」と、助言してくれる人がいました。
それ以来この方法で糸通しをしていましたが、細い針金を使った糸通しの道具を見つけました。これは便利です。
糸通しひとつにしても、やり方は色々あるものです。人生の様々な場面においても、解決策は一つではないと思います。
自分一人では困難なことも、他の力を借りれば乗り越えられる方策が必ず見つかります。
一人で抱え込まず、肩の力を抜いて、他に頼ることも時には大切なことではないでしょうか。
令和4年3月
~日蓮聖人のお手紙より~
世間の法には慈悲なき者を邪見の者という
先日、ロシアがウクライナに侵攻しました。どんな政治的理由があろうとも武力行為は容認されるものではありません。現地で恐怖と不安の日々を送っている人のことを思うと不憫でなりません。
仏教には「慈悲(じひ)」ということばがあります。
慈悲とは、「慈(いつく)しみ」の心と「憐(あわ)れみ」の心のことで、人として持たなければならない大切な心です。
いつくしみ とは、我が子を思うような深い愛情
あわれみ とは、他者の悲しみを思いやる感情
この慈悲の心が薄くなれば、人は自己中心的になり、邪(よこしま)な考えに陥ります。そんな人が増えれば、道理がとおらなくなり、社会は不安になります。社会が不安になれば、個々の幸せも実現しません。日蓮聖人は、世の中に背く人のことを「邪見の人」と言って、正しい モノの見方ができない愚かな人のことを示されています。
私たちは自分の中の慈悲の心と向き合い、他者の幸せを祈れる深い心持ちを抱きたいものです。ウクライナに一刻も早く平和がおとずれるようにお祈りします。
令和4年2月
~日蓮大聖人のお手紙より~
一日の命は三千界の財にもすぎて候なり
命は三千にもすぎて候ふ一日も生きてをはせば
功徳つもるべし
昨年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。選手の活躍によって世界中の人びとが一喜一憂し、感動をもたらしてくれました。
わたしたちにとっての喜びとは一体なんでしょう?
家族の幸福でしょうか。いつも健康でいられる事でしょうか。愛する人と一緒にいられることかもしれませんね。
日蓮聖人は「今日生きたこと」は何よりも尊く、すばらしい事だと言っています。生きたことで徳を積んだことになる。その積み重ねの事を「功徳」と言います。
世の中に大変な日々が続いていますが「今日生きたこと」で「明日も生きてみよう」と自分に言い聞かせることで人間は成長していくものです。
令和4年1月
一心に仏を 見たてまつらんと欲して 自ら身命を惜しまず
「妙法蓮華経如来寿量品第十六」
新春を迎え、一家そろってお雑煮を食べ、初詣をするのは、多くの日本人の習慣になっています。これをしなければ、お正月らしくないという人が多いのではないでしょうか。
新年を無事に迎えることができるのも、絶えることなく生命を繋ぎつづけてくれた、多くのご先祖さまのおかげです。人として生まれ、今もこうして生きていることを深く感謝することで、1年の始まりとしたいものです。そのために初詣には、まず菩提寺をお参りし、お墓参りをして新年の始めとしましょう。
「一心」とは、自分の心を一つのことに集中すること。「身命を惜しまず」とは、精一杯に心と体で動くこと。初詣の際に手を合わせている時の私達の心のあり方、つまり素直な気持ちで「一心」に手を合わせる心が仏心であり、ひるがえってみればそれぞれの“いのち”を生かす原動力につながっていくことを忘れないよう過ごし、よりよい1年になるよう共に精進しましょう。